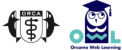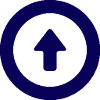ICT中級講座 F/U NO.23
メディカルICTリーダー養成講座【中級】フォローアップ
≪サーバー保守学≫
医療現場のサーバーやシステム保守運用業務に役立つ情報を定期的に配信しています。
サーバ保守学(22)
(執筆者)亀田医療情報株式会社 塚田智
みなさん、こんにちは、サーバー保守学第22回です。新型コロナウイルスの感染拡大は第4波に入ったようです。毎日のように感染者が増え、各地にまん延防止措置が出されています。さらに、3度目の緊急事態宣言が発令されました。感染拡大に伴い、コロナ関連で入院する患者さんも増え、コロナ対応の医療機関は、昨年末と同じかそれよりも逼迫した状況でしょう。先が見えないストレスの多い期間が続きますが、それぞれの立場でいまやるべきことを正しく認識して、丁寧に対応していきましょう。
さて今回は、電子カルテのシステムやデータのバックアップの失敗と、バックアップから元通りのシステムやデータを復元するタスクの失敗について考えます。バックアップと復元は、どのような理由で失敗するのか、失敗のリスクを削減する対策は何か、考えていきましょう。
バックアップと復元の失敗(1)
1.バックアップの失敗
バックアップには、システムバックアップとデータバックアップがあります。システムバックアップは、サーバーやVMのシステム全体が対象です。データバックアップは、データベースやファイルサーバーのデータが対象です。これらのバックアップが失敗する要因としては、バックアップ先の容量が不足していた、バックアップのタスクが起動しなかった、などが考えられます。
バックアップの一連の操作を自動化するために、バックアップ管理ソフトがあります。管理ソフトは、システムやデータベースに指示を出してバックアップデータを作成し、それを取得して適切な場所に移動し、世代管理することができます。この過程で失敗することがあります。
- 管理ソフトが指示したのに、システムやデータベースが何らかの理由で、バックアップデータを作成できなかった。
- バックアップデータを移動しようとしたが移動先の容量が不足していた、または移動先が存在しなかった。
- 移動先がテープドライブの場合。テープの入れ忘れ、またはテープの入れ間違いがあった。
- 管理ソフトの設定ミスで、タスクが適切なタイミングで実行されなかった。
このようにバックアップは、システム、データベース、管理ソフト、ハードウェアに関連しています。これらがすべて適切に設定され、正常に動作していないとバックアップは成功しません。バックアップは、システム運用の中でも比較的失敗しやすいタスクなのです。
2.バックアップの失敗の対策
これらの失敗のリスクに対して、どのような対策がとれるでしょうか。まず、バックアップ管理ソフトで操作を自動化することができます。これである程度はリスクを削減できますが、まだ不十分です。自動化した上で、定期的に管理ソフトの画面上で設定と実行結果を確認する必要があります。さらに、管理ソフトの対象外になるものは、人による確認が必要です。例えば、移動先の空き容量の確認、テープ挿入のダブルチェック、などがです。
バックアップは、週末や夜間で業務がピークでない時間帯に実行されるように設定してあることが多いです。また、失敗しても即時に業務に影響しないため、失敗に気付きにくいという特徴があります。つまり、普段は使わないデータなので注意が払われないことが多いのです。また、管理ソフトによるバックアップの実行は、医療機関の業務フローに直接関係しないので、システム管理者にとってあまり馴染みがないかも知れません。しかし、システムにとってバックアップはとても重要なものです。必ず実行結果を確認し、バックアップデータを厳格に管理する必要があります。そのために日頃から管理ソフトを使うことで、バックアップの仕組みを深く理解できるようになります。これにより、システムやデータベースを復元する作業もスムーズに行えるようになることが期待できます。
これらの明らかな失敗だけでなく、バックアップの経過時間が長くなり、業務のピーク時にもタスクが実行され続け、システムのレスポンスが悪化することもあります。このような場合は、バックアップの対象を削減する、タスクを分割して並列に実行する、バックアップ先のストレージの性能を改善する、などの対応が必要になります。この対応は難易度の高いものです。事前の対策としてバックアップの実行時間を確認して、大きな問題になる前に少しずつ対応しておくことも必要です。
今回はバックアップの失敗とその対策を考えました。次回は、バックアップからの復元について、その失敗と対策を考えましょう。