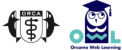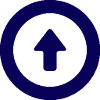オベリスク F/U
会員制倶楽部オベリスク フォローアップ
≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。
2021年9月24日のヘッドライン
- やり切ろう、ワクチン。考えよう、Postコロナ。コロナワクチン職域接種全く振わず。
官邸一週間分を公表。7日で70万回の接種回数増に止まる。一日当たり10万回。
うち2回目は3万回余、1回目が7万回弱。
———————————————————–
◇国内の新型コロナワクチン接種回数・接種率等☞首相官邸HP
◇国内の新型コロナ感染者数状況☞NHKオンライン
- 脱ステロイド「療法」を番組で紹介した日本テレビに抗議 <日本皮膚科学会>
日本皮膚科学会は9月14日、「ひどい肌荒れ」に対する脱ステロイド「療法」が、番組内で好意的に紹介されたことについて日本テレビに抗議したことを明らかにした。問題となったのは9月7日放送の「ザ!世界仰天ニュース」で、「ステロイド薬の使い過ぎにより体内でステロイドが作られなくなった。再び体内で作られるようにするには、ステロイド薬を断つしかない」などと、科学的根拠のない脱ステロイド「療法」を紹介した。これに対し同学会は、日本アレルギー学会、日本臨床皮膚科医会、日本皮膚免疫アレルギー学会、日本小児アレルギー学会、日本小児皮膚科学会、日本アレルギー友の会(患者会)と連名で抗議文を同局に提出、番組内容について、ステロイド外用薬使用中の患者の恐怖と不安をあおる一方、「療法」という用語を使うことにより、ステロイド外用薬を使わないことに対し、「一つの治療法としてあたかも疾患が治るかのごとき期待を抱かせるもの」と厳しく非難した。さらにアトピー性皮膚炎診療ガイドラインに沿って診療している医師を妨害し、多くの健康被害をもたらす可能性が高いと強く抗議した。日本テレビは翌15日に謝罪放送を行い、番組ホームページでも謝罪表明している。
◎参考サイト:【重要】2021年9月7日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」に関して抗議文を提出したことについて
◎参考サイト:番組ホームページ(謝罪文掲載・9月16日閲覧)
- ロナプリーブ投与後、新型コロナワクチン接種までの間隔は「3カ月程度」 <厚生労働省>
厚生労働省は9月10日付の事務連絡で、新型コロナ中和抗体薬ロナプリーブに関する質疑応答集の修正・追加を示した。今回、追加された「ロナプリーブ投与後に、新型コロナのワクチン接種は可能か?」という質問に対しては、同剤とワクチンとの相互作用に関するデータは得られていないが、抗体が身体に残っている間はワクチンの効果が弱まる可能性を指摘。そのうえで「3カ月程度は空けることが望ましい」とする米国疾病予防管理センター(CDC)の見解も踏まえ、医療現場において判断するよう求めた。事務連絡はそのほか、同剤を投与できる医療機関のリストを都道府県が作成、軽症患者が受診する可能性が高い診療所などに提供し迅速な投与につなげる取り組みも求めた。
◎参考サイト:新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分について(質疑応答集の修正・追加)【PDF】
(公開日 : 2021年09月24日)

日本商工会議所プログラミング検定研究会監修 C言語で未来を動かせ!
日商検定対策プログラミング応用講座-C言語編-
「日商プログラミング検定 STANDARD(C言語)」の合格を目指しながら、プログラミングの基本や考え方を丁寧に学べます。忙しい方でも無理なく進められるカリキュラムで、C言語の“しくみ”を理解して、“使える力”へ。「これからプログラミングを始めたい方」にも、「仕事に活かせるようになりたいという方」にもおすすめです。