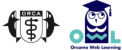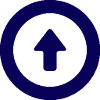オベリスク F/U
Obelisk フォローアップ
≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。
2022年10月17日のヘッドライン
- やり切ろう、ワクチン。考えよう、ポストコロナ。コロナワクチン長引く副作用の実態調査。厚労省実施へ。
「原因不明」に終わらぬよう、実施責任者の選任が重要。客観性のある人材の起用を。
日本の直近一日当たりコロナ死者数は47人。
直近の一日当たりのワクチン3回目接種者2万6千人。累計は82,654,171人。接種率65.6%。
4回目は一日当たり17万2千人。累計は36,654,964人。
———————————————————–
◇国内の新型コロナワクチン接種回数・接種率等☞首相官邸HP
◇国内の新型コロナ感染者数状況☞NHKオンライン
- 介護医療院の経営、悪化傾向に <福祉医療機構>
福祉医療機構は9月29日、2021年度の介護医療院の経営状況に関するリサーチレポートを公表した。2019年度と比較すると、経常利益率は4.3ポイント減の4.4%、事業利益率は4.5ポイント減の4.0%、赤字施設割合は19.3ポイント増の31.8%となった。利益率減少の要因として同機構では、介護療養病床などからの「移行定着支援加算」の廃止と、新たに創設された長期療養生活移行加算の算定率の低さを挙げた。施設類型別では、Ⅰ型よりもⅡ型のほうが、入所定員1人当たり事業収益などが低く、赤字施設割合は高かった。また、人件費率の上昇により、Ⅰ型・Ⅱ型ともに、2020年度から事業利益率や形状利益率が低下していることもわかった。同レポートの調査対象は、同機構の貸付先に限られ、サンプル数は今回85施設にとどまる。同機構ではそれを踏まえ、「レポートは全国の介護医療院の状況を反映していない可能性があること」について、留意を求めている。ちなみに今年6月末の介護医療院は727施設(Ⅰ型492施設、Ⅱ型230施設、Ⅰ・Ⅱ型混合5施設)となっている。
◎参考サイト:2021年度(令和3年度)介護医療院の経営状況に関するリサーチレポートについて【PDF】
- 高齢者1人当たりの年間介護費、市町村間で最大4倍の開き <筑波大>
筑波大学は9月30日、医学医療系・田宮菜奈子教授らの研究グループが、2019 年度の「介護保険事業状況報告」と「社会・⼈⼝統計体系」のデータを⽤い、市区町村における⾼齢者1⼈当たりの年間介護費の地域差を把握し、その差を説明できる要因を解析した結果を公表した。解析対象となった 1,460⾃治体で、⾼齢者1⼈当たり年間介護費は約 13万円〜55万円と4倍の開きがあり、⾃治体ごとの年齢・性別の分布を統計学的に調整後も、3.6倍と⼤きな地域差があった。地域差を説明できる要因としては、⾃治体における要介護認定率及び重度要介護者の割合の⾼さの説明率が⾼いことが明らかになった。研究グループでは、「本研究の結果を基に、介護費の⾼い⾃治体においては、介護予防対策などを実施して要介護認定率や重度要介護者の割合を改善し、それが介護費低下につながるかを検証していくことが望まれる」としている。
◎参考サイト:プレスリリース【PDF】
(公開日 : 2022年10月17日)

日本商工会議所プログラミング検定研究会監修 C言語で未来を動かせ!
日商検定対策プログラミング応用講座-C言語編-
「日商プログラミング検定 STANDARD(C言語)」の合格を目指しながら、プログラミングの基本や考え方を丁寧に学べます。忙しい方でも無理なく進められるカリキュラムで、C言語の“しくみ”を理解して、“使える力”へ。「これからプログラミングを始めたい方」にも、「仕事に活かせるようになりたいという方」にもおすすめです。