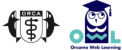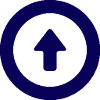オベリスク F/U
Obelisk フォローアップ
≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。
2024年12月24日のヘッドライン
- 若手医師コスパの悪い保険医療から離脱の動き。
安い給与と夢の無い将来性に見切りをつけ、自分のリスクで自由診療の道選択。
医師国家資格合格者年間8000人強。1割離脱するだけで、日本の医療制度崩壊もあり得る。
根本的な問題は日本の医療財源の少なさ。厚労省には自由診療分野の健全な育成策の構築を望みたい。
束縛すれば人が動く時代は終わった。
- 定期的血糖測定を行わずステロイド増量、患者死亡 <千葉県がんセンター>
千葉県がんセンターは12月13日、食道神経内分泌がんで治療中の患者が、2021年6月に糖尿病性ケトアシドーシスで死亡していたことを明らかにした。患者は当時60歳代男性。脳転移による痙攣のため、抗てんかん薬とステロイドの内服を行っていたが、脳転移巣の増大と脳浮腫の悪化でステロイドを増量した11 日後、多臓器不全により死亡した。外部委員を含めた院内事故調査委員会は、ケトアシドーシスは、がんの進行などによる慢性的高血糖状態の中で、定期的な血糖測定や高血糖状態への治療介入もないままステロイドを増量したことが誘因となり発生したと結論づけた。また再発防止策として、▼がん薬物療法中患者の定期的な血糖測定の義務化▼多職種による血糖確認体制、標準化された低血糖/高血糖対応の定着に取り組む▼糖尿病専門医による外来の開設と、他の専門医療機関との連携強化――を挙げた。
◎参考サイト:千葉県がんセンターにおけるアクシデントの発生について
- 診断に懸念抱いても、医師にはなかなか伝えられない看護師 <順天堂大学>
順天堂大学は12月4日、看護師が医師の診断に懸念を抱く頻度や、その懸念を医師に伝えられたかどうかなどを調べた研究結果を公表した。医師と看護師から成る研究チームは、日経メディカル社に登録している看護師を対象に、6月から7月にかけて調査を実施。430人から回答を得た。回答者のうち女性は81.2%、年齢の中央値は45歳、経験年数の中央値は19年だった。また管理職は回答者全体の28.3%、何らかの専門スキルを所持している看護師は24.0%だった。1カ月以内に医師の診断に懸念を感じた看護師は61.2%で、経験年数が長いほど懸念を感じやすいことも判明した。感じた懸念を医師に伝えられなかった看護師は52.5%で、看護師の経験年数が長いほど懸念を伝えられず、さらに病床数が少ない病院や診療所のほうが伝えにくい傾向にあった。伝えられない理由のトップ5は、医師のプライドを傷つけてしまうから(21.1%)、懸念を伝えても無視されるから(18.6%)、診断は医師がするものだから(15.7%)、医師を怒らせてしまうから(14.3%)、診断アセスメントに自信がないから(12.1%)という結果だった。研究チームでは、この結果について「想定以上に看護師は医師の診断に懸念を感じていることに驚いた」「特に懸念を伝えられない理由から鑑みるに、医師要因と看護師要因の両方があり、この両方向からの対策が重要であると思われた」としている。
◎参考サイト:ニュース&イベント
(公開日 : 2024年12月24日)

日本商工会議所プログラミング検定研究会監修 C言語で未来を動かせ!
日商検定対策プログラミング応用講座-C言語編-
「日商プログラミング検定 STANDARD(C言語)」の合格を目指しながら、プログラミングの基本や考え方を丁寧に学べます。忙しい方でも無理なく進められるカリキュラムで、C言語の“しくみ”を理解して、“使える力”へ。「これからプログラミングを始めたい方」にも、「仕事に活かせるようになりたいという方」にもおすすめです。