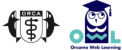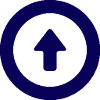ICT中級講座 F/U NO.22
メディカルICTリーダー養成講座【中級】フォローアップ
≪サーバー保守学≫
医療現場のサーバーやシステム保守運用業務に役立つ情報を定期的に配信しています。
サーバ保守学(21)
(執筆者)亀田医療情報株式会社 塚田智
みなさん、こんにちは、サーバー保守学第21回です。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言は、ようやく解除されました。まだ感染者は多いですが、少しは落ち着いた雰囲気があります。今後は爆発的な感染拡大が起こらないように、日常的な感染防止対策を継続していくことが大切だと思います。医療機関の運用も、これまでのような一時的な対応から、継続的な対応に移っていきます。それに合わせて運用フローやシステムも変更しなくてはなりません。引き続き丁寧に対応していきましょう。
さて今回は、電子カルテなどのアプリケーションに追加された新機能を、現場で利用していく手順を考えます。医療機関に導入されているシステムは、2年に一度の診療報酬改定の影響を受けます。最近では、平成から令和への改元、オンライン資格確認の開始、などがあり毎年のようにアプリケーションが更新されます。これ以外にも機能範囲の拡大や利便性の向上のために新機能が頻繁に追加されます。これらの新機能をどのように利用開始すべきか考えてみましょう。
新機能の利用開始は、即時にまたは計画的に
1.新機能は全部確認して選択する
アプリケーションにどのような新機能が追加されたかのは、アプリケーション開発業者から「リリースノート」のよう形で情報提供されます。提供の間隔は月1回から年1回くらいまで業者によって異なります。業者としては、なるべく早くユーザーに提供したいのですが、提供するには業者の手間もかかります。そのため、多くても月1回くらいが目標になっています。
システム管理者は、業者から提供された情報を全部確認し、理解しなくてはなりません。情報提供が不十分で内容を理解できない場合は、遠慮なく業者に問合せましょう。理解できずに新機能を使えないのは、現場、システム管理者、業者のすべての関係者にとって不利益なことです。
新機能が提供されたからといって、それらを自施設で全部使う必要はありません。業者はいろいろなユーザーの意見を集めて新機能を作っています。その中には自施設には不要な新機能も含まれています。自施設の特性や運用に合わせて必要な新機能を選択しましょう。
2.即時に利用開始できるもの
新機能には即時に利用できるものがあります。それは、障害を修正するもの、処理速度を速くするもの、軽微な機能追加など現場の運用に影響が無いものです。これらは出来るだけ早く利用開始しましょう。
業者にもよりますが、業者からアプリケーションの修正モジュールが配布され、自施設のシステムにはシステム管理者が適用することがあります。この場合には、できるだけ早く適用できるように、手順に慣れておきましょう。適用が遅れると、適用する前に次の新機能が提供され、それが蓄積して現在利用しているものとの差分が大きくなります。これをまとめて適用してしまうと、適用前後の操作に戸惑うことになり、システム全体の評価が下がってしまいます。
3.計画的に利用開始するもの
新機能は、できるだけ即時に利用開始すべきです。しかし、計画的に利用開始したほうが、運用がうまくいくものもあります。現場の運用に影響が大きく、利用のために運用フローの変更や操作説明が必要なものや、マスターの整備に時間がかかる新機能がこれにあたります。例えば、いままで紙運用が残っていた業務を、新機能を使って紙を無くすような場合です。
業者からの提供時期に合わせて、自施設のリリース時期を決めておくのが良いでしょう。業者から毎月提供されるのなら、自施設には2週間後に毎月適用し、運用フローに影響しないものを即時に利用開始し、運用フローに影響するものは、3か月に1回利用開始する、という手順です。
診療報酬改定のように、利用開始の時期が決まっていて、事前に十分な準備できない場合もあります。このような場合は、暫定的な運用フローで期限までに利用開始します。そして、暫定的な運用から3か月後までに十分な準備をして、継続的な運用フローに変更するといった工夫も必要です。
新機能を使うと現場から、ボタンの位置が変わった、色が変わった、文字の大きさが変わった、前のほうが使いやすかった、など否定的な意見も多く出されます。これを恐れてシステムを古いままにしておくと、診療報酬改定などの新機能を適用しなくてはならないときにとても困ります。新機能はできるだけ頻繁に自施設にも適用しておくことで、現場には、システムは頻繁に変わるものなのだ、という認識を持ってもらいましょう。そうすることで、全体として変化に強いシステムと運用を実現できると思います。