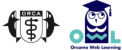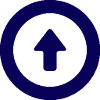オベリスク F/U
会員制倶楽部オベリスク フォローアップ
≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。
2021年8月13日のヘッドライン
- やり切ろう、ワクチン。考えよう、Postコロナ。コロナワクチン職場接種1回目、伸び鈍く。この一週間で30万回増に止まる。
全国民の2回目接種は11日一日で75万回増で接種36.1%に。
うち高齢者分は23万回。政府目標の500万回まであと410万回。 - 樹状細胞がアトピー性皮膚炎の増悪化を阻止する仕組みを発見 <宮崎大学>
宮崎大学は7月27日、医学部の佐藤克明教授と天野正宏教授の共同研究チームが、樹状細胞がアトピー性皮膚炎の増悪化を阻止する仕組みを発見したと発表した。研究チームは樹状細胞を欠損させたマウスと通常の野生型マウスの比較実験を実施。その結果、樹状細胞欠損マウスでは野生型に比べ、免疫組織における顆粒球(好酸球、好中球、好塩基球/肥満細胞等)の割合の増加、血清中における炎症を誘発したり免疫細胞を増やしたりするサイトカインやIgE、IgGの増加、皮膚細胞におけるアレルギー性炎症に関わる遺伝子の発現亢進やフィラグリン遺伝子の発現低下――などが認められたという。また実際に、樹状細胞欠損マウスでは皮膚のバリア機能が壊れ、黄色ブドウ球菌が定着し、野生型に比べ症状が悪化したことも確認した。これまでアレルギー疾患は、樹状細胞が病原性微生物を捕食することにより開始すると考えられてきたが、これらの結果から研究チームでは、「樹状細胞は、アトピー性皮膚炎の発症や増悪化には必要ではなく、むしろ免疫バランスを維持することにより、アトピー性皮膚炎の増悪化阻止に作用するという重要な知見を得ることができた」としている。
◎参考サイト:プレスリリース
- NDBを活用し、中心性漿液性脈絡網膜症の発症率や発症傾向を明らかに ≪京都大学≫
京都大学は7月19日、三宅正裕・医学研究科特定講師らの研究グループが、厚生労働大臣の許可のもと、ナショナルデータベース(NDB)の全データを解析することにより、日本人の中心性漿液性脈絡網膜症の発症率や性別・年齢による発症傾向を明らかにしたと発表した。日本のほぼ全国民のレセプト情報が含まれているNDBを解析した同研究は、中心性漿液性脈絡網膜症の疫学研究として世界最大の報告で、NDBオンサイトリサーチセンター(京都)を活用した初の成果という。同研究グループは、今後もNDBをはじめとしたレセプトデータベースを用いて、中心性漿液性脈絡網膜症のみならず種々の眼科疾患の疫学や発症リスクを解明し、病態解明や新たな治療法の発展につなげていくという。
◎参考サイト:プレスリリース
(公開日 : 2021年08月13日)

日本商工会議所プログラミング検定研究会監修 C言語で未来を動かせ!
日商検定対策プログラミング応用講座-C言語編-
「日商プログラミング検定 STANDARD(C言語)」の合格を目指しながら、プログラミングの基本や考え方を丁寧に学べます。忙しい方でも無理なく進められるカリキュラムで、C言語の“しくみ”を理解して、“使える力”へ。「これからプログラミングを始めたい方」にも、「仕事に活かせるようになりたいという方」にもおすすめです。