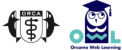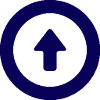人事労務 F/U NO.68
人事労務基礎講座 フォローアップ
≪判例・事例紹介、法改正情報など≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。
1.月88,000円を超えたり超えなかったり…パートの社会保険はどうなる?
2.カスハラ防止措置義務化へ
(執筆者)社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所
1月88,000円を超えたり超えなかったり…パートの社会保険はどうなる?
現在パートで働いています。月収88,000円を超えたら社会保険に加入すると聞きました。月によって超えるときと超えないときがあるのですが、どう判断するのでしょうか?
実際に支払われた賃金の額で判断するのではなく、契約書で定めた賃金の額で判断します。
* * * * *
現在、社会保険の適用拡大が進められており、パートタイマーでも要件を満たす場合は社会保険に加入しなければなりません。以前は101人以上の企業で働くパートタイマーが対象でしたが、2024年10月からは、これが51人以上の企業に拡大されています。
① 社会保険に加入するパートタイマーの要件
51人以上の企業で次の4つの要件をすべて満たすパートタイマーは、社会保険に加入しなければなりません。
- 労働時間が週20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込み
- 学生ではない
このうち、2.の要件については、どのように判断すべきか迷う場面が多く、ご質問の多い部分です。以下、よくある質問にお答えしていきます。
② 月によって88,000円を超えるときと超えないときがある
「実際に支給された賃金がいくらか」ではなく、所定内賃金、つまり「契約書で決めた賃金がいくらか」で判断します。
たとえば、一時的に忙しく残業などで月88,000円以上となることがあったとしても、契約書では88,000円未満であれば、2.の要件を満たさず加入対象とはなりません。
ただしその場合でも2ヵ月以上88,000円以上となり、その状態が続くようであれば3ヶ月目から加入対象となります。
③ 時給制の場合、月額賃金はどのように計算する?
パートタイマーの場合、月給制ではなく時給制の人が多いでしょう。
その場合は、雇用契約等にもとづいて、次のように計算します。
年に52週(月に4.3週)あるものとして計算するということです。
この額が88,000円を超えているかどうかで判断します。
契約書では1日の労働時間と週の労働日数しか定めていないという場合は、1日の労働時間×週の労働日数で週の所定労働時間が分かります。
④ 加入後につき88,000円を下回ったら資格を喪失する?
社会保険に加入した後、欠勤などによってたまたま月88,000円を下回る月があったとしても、それで資格を喪失することはありません。
ですが、雇用契約等が見直され、所定内賃金が月額88,000円を下回ることが明らかになった場合は資格を喪失します。また、雇用契約に変更はなくても、常態的に88,000円を下回る状況が続くことが確認できる場合も実態をふまえた上で資格を喪失します。
⑤月額88,000円には残業代や通勤手当も含まれる?
月額88,000円の算定対象は、基本給と諸手当で判断します。ただし、以下の賃金は算入されません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外や休日・深夜労働の割増賃金等
- 最低賃金において参入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
つまり、残業代や通勤手当は除いた金額で月額88,000円以上となるかどうかを判断します。
なお、標準報酬月額(※)を算定するときは、賃金に含めるもの・含めないものの範囲がちがうので、ここは混同しないよう注意が必要です。
(※)社会保険料の計算基準となるもの
2カスハラ防止措置義務化へ
顧客による迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題となっています。
東京商工リサーチが8月上旬に実施した調査によると、「カスハラ」を受けたことがある企業が約2割(19.1%)あることがわかりました。業種別では、「宿泊業」、「飲食店」が上位に並んでいます。
カスハラの影響で「休業や退職の発生」に追い込まれた企業も13.5%ありました。調査結果をみると、「ハラスメントする企業とは取引中止」、「地元警察と連携し、特に悪質な場合の通報体制を整えた」、「従業員ではなく代表が対応」など、研修や対応方針の策定、相談窓口の設置などの対策を講じている企業もあることがわかります。
ですが、「対策を講じていない」と回答した企業が7割超あり、カスハラ被害の広がりへの対策が遅れている実態も浮き彫りになりました。
① 報告書でカスハラ防止措置の義務化を提言
こうした状況の中、厚生労働省の有識者検討会が重要な報告書をまとめました。この報告書では、企業に対してカスハラ防止措置を義務付けることが適当であるとの提言がなされています。
具体的な防止措置の内容については、既存のパワハラ防止措置などを参考にしつつも、カスハラ特有の性質を考慮して検討する必要があるとしています。
② 行為者は取引先や一般消費者
カスハラの場合、行為者が顧客や取引先といった第三者であるため、主に企業内の労働者が行為者となるパワハラなどとは異なるアプローチが求められます。さらに、行為者が取引先であるか一般消費者であるかによっても、適切な対応が異なる可能性があります。
このような複雑な特性を持つカスハラに効果的に対処するためには、現場での実際の状況や企業の対応能力も十分に考慮しながら、きめ細やかな検討を進めることが重要です。