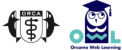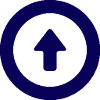オベリスク F/U
Obelisk フォローアップ
≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。
2022年9月6日のヘッドライン
- やり切ろう、ワクチン。考えよう、ポストコロナ。コロナ後増税 物言わぬ高齢者から。
後期高齢者医療保険の保険料アップ。介護保険の自己負担率も実質拡大。2023年度から。
日本の直近一日当たりコロナ死者数は221人。
直近の一日当たりのワクチン3回目接種者4万7千人。累計は81,654,115人。接種率64.8%。
4回目は一日当たり4万6千人。累計は28,454,158人。
———————————————————–
◇国内の新型コロナワクチン接種回数・接種率等☞首相官邸HP
◇国内の新型コロナ感染者数状況☞NHKオンライン
- 乳がん治療中では、コロナワクチンの効果低下も <名古屋市立大>
名古屋市立大学は8月12日、乳がん治療と新型コロナワクチンの関連を検討する多施設共同前向き観察研究の結果を公表した。2021年5月~11月に新型コロナワクチン接種予定の乳がん患者を対象とし、ワクチン接種前と2回目接種後4 週で血清を採取。受けている5種の治療別にグループ分けし、SARS-CoV-2 S蛋白に対するIgG濃度、および野生・アルファ・デルタ・カッパ・オミクロン株に対する中和抗体価を測定した。その結果、2回接種後の抗体陽性率は95.3%と高かったが、化学療法またはCDK4/6阻害薬で治療中の場合、抗体が陽転化しても変異株によっては中和抗体価が低くなっている場合があったという。この結果について研究グループでは、「2回接種後であっても感染予防のための行動が大切であることが示唆された」としている。また、化学療法やCDK4/6 阻害薬投与中に中和抗体価が下がる理由は不明で、「薬物治療中の免疫状態についてはまだまだわかっていないことが多く、今後の検討課題」とした。
◎参考サイト:プレスリリース【PDF】
- オキシトシンを「見える化」するツールの開発と応用に成功 <慶應大>
慶應義塾大学は8月26日、同大の研究グループが、脳内の神経伝達物質であるオキシトシンを「見える化」するツールの開発と応用に成功したと発表した。オキシトシンは、分娩促進や母性行動のほか、人間関係を築いていく社会的行動でも重要な役割を果たすとされているが、これまで直接見ることができなかった。無色透明で、分子量が非常に小さいため、蛍光標識(タグ)を付加すると、本来の動きや性質に影響を与えてしまい、真の姿をとらえることができなかったためだ。そこで今回の研究では、極小タグであるアルキン(アセチレン系炭化水素)をオキシトシンに付加した「アルキンオキシトシン」を開発。これを、さまざまな条件下でマウスの生きた脳組織に適用することにより、これまで謎に包まれてきたオキシトシンの脳内における作用部位や時空間的動態をとらえることに初めて成功したという。研究グループでは、「本研究成果により、オキシトシンをはじめとするさまざまな伝達物質が見える化され、まだまだ謎の多い精神機能の分子基盤への理解が深まり、脳研究を大きく前進させることが期待できる」としている。
◎参考サイト:プレスリリース
(公開日 : 2022年09月06日)

日本商工会議所プログラミング検定研究会監修 C言語で未来を動かせ!
日商検定対策プログラミング応用講座-C言語編-
「日商プログラミング検定 STANDARD(C言語)」の合格を目指しながら、プログラミングの基本や考え方を丁寧に学べます。忙しい方でも無理なく進められるカリキュラムで、C言語の“しくみ”を理解して、“使える力”へ。「これからプログラミングを始めたい方」にも、「仕事に活かせるようになりたいという方」にもおすすめです。