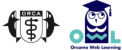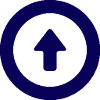オベリスク F/U
Obelisk フォローアップ
≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。
2023年5月29日のヘッドライン
- 健康第一、換気・うがい・手洗いで。マイナンバーカードの活用拡大に不安を感じている人28.3%。全く不安を感じていない人6.6%。
ある程度不安を感じる余り不安を感じないの中間層の合計が63.9%。
不安を感じているかいないかで区分すると7割対3割。共同通信社全国電話調査による。
このデータではマイナ保険証一本化は無理。健康保険証は現行保険証との併行運用が現実的。
———————————————————–
◇国内の新型コロナワクチン接種回数・接種率等☞首相官邸HP
◇国内の新型コロナ感染者数状況☞NHKオンライン
- 2021年度、特定健診実施率は56.5% <厚生労働省>
2021年度の特定健康診査の対象者数は約5,380万人、受診者数は約3,039万人であり、実施率は前年度比3.1ポイント増の56.5%だったことが、厚生労働省が5月10日に公表した2021年度分の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」でわかった。特定保健指導の実施率は前年度比1.6ポイント増の24.6%だった(対象者数:約526万人、特定保健指導を終了した者:約129万人)。保険者別の(特定健診実施率/特定保健指導実施率)は、市町村国保(36.4%/27.9%)、国保組合(49.0%/13.2%)、協会けんぽ(55.9%/16.5%)、船員保険(52.0%/13.4%)、健保組合(80.5%/31.1%)、共済組合(80.8%/31.4%)となっている。メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率(対2008年度比)は、前年度比2.9ポイント向上し13.8%だった。ちなみに国は2023年度までに、特定健診/特定保健指導の実施率を70%以上/45%以上、メタボ該当者及び予備群の対2008年度比減少率を25%以上とすることを目標としている。
◎参考サイト:2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況
- 入浴時に石けん類の使用頻度が少ないと、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーの発症が多い <富山大>
富山大学は5月12日、同大附属病院小児科の研究グループが行った入浴時の石けん類使用頻度とアレルギー疾患の発症の関連についての調査結果を公表した。研究グループは、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」の参加者74,349名を対象に、母親へのアンケート調査を実施。1歳半の時に入浴時に石けん類を使う頻度は、「毎回使う」が9割と大多数を占めたものの、「だいたい使う」「ときどき使う」「ほとんど使わない」子どもも一定数いた。そこで、「毎回使う」子どもを基準とした場合の、「だいたい使う」「ときどき使う」「ほとんど使わない」子どもおける、3歳時点でのアトピー性皮膚炎、食物アレルギー、ぜん息の診断状況を調べた。その結果、1歳半時点の入浴時の石けん類使用の頻度が少ない子どもでは、3歳時点でアトピー性皮膚炎と食物アレルギーと診断されている子どもが多くなる傾向が見られた。ぜん息に関しては入浴時の石けん類使用の頻度との関連は認められなかった。
◎参考サイト:プレスリリース
(公開日 : 2023年05月29日)

日本商工会議所プログラミング検定研究会監修 C言語で未来を動かせ!
日商検定対策プログラミング応用講座-C言語編-
「日商プログラミング検定 STANDARD(C言語)」の合格を目指しながら、プログラミングの基本や考え方を丁寧に学べます。忙しい方でも無理なく進められるカリキュラムで、C言語の“しくみ”を理解して、“使える力”へ。「これからプログラミングを始めたい方」にも、「仕事に活かせるようになりたいという方」にもおすすめです。