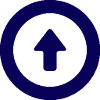人事労務 F/U NO.3
人事労務基礎講座 フォローアップ
≪判例・事例紹介、法改正情報など≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。
[事例研究]認知症患者と介護者の責任
(執筆者)日本医師会総合政策研究機構 主任研究員 王子野麻代
(法律監修)銀座中央総合法律事務所 弁護士 高山烈
高齢化の進展に伴い、認知症患者が増加しており、2025年には約700万人に及ぶと言われている(注1)。認知症を根治する治療薬がない現状では、症状の進行をゆるやかにして“見守る”ことが最善策となるが、介護者にも限界がある。
近年、介護者の気づかぬ間に、認知症患者が一人で外出して行方不明になる事件が多発しており (注2)、中には交通事故に巻き込まれて死に至るケースさえある。たとえば、平成19年には、認知症患者が一人で外出して駅構内の線路に立ち入り、列車に衝突して亡くなる事故が起きている。これに対し、鉄道会社が、事故による列車の遅延損害等の賠償を求めて、認知症患者の妻と長男に対して監督義務者責任等を争ったことで、多くの人々の注目を集めた。
認知症患者が起こした他害事故。家族だからその責任を問われるのか? 夫婦だから? 同居してたから? 介護に携わっていたからなのか? 認知症の家族を抱えている方々にとって、他人事とは思えない話である。以下、事案の概要と最高裁の判例を中心に紹介する。
1.事案の概要
- Aは、大正5年生まれ、昭和20年に婚姻し、以後同居していた。
- 平成12年12月頃から、認知症らしき症状がみられるようになった。
- 平成14年8月頃の入院を機に、認知症の悪化をうかがわせる症状あり。
- 平成15年3月に病院を受診した際、平成14年10月にはアルツハイマー型認知症に罹患していたと医師の診断を受けた。
- 平成16年2月、Aは場所と人物に関する見当識障害や記憶障害が認められ、認知症の症状はおおむね中等度から重度に進んでいる旨、医師に診断された。
- 平成17年以降に2回、早朝または深夜に一人で外出して行方不明となり、警察に保護されたことがあった。これらの出来事を受けて、Aの妻と長男は、Aが知らぬまに外出したときに備えて様々な工夫をした。たとえば、警察にあらかじめ連絡先等を伝え、Aの上着等には名前や携帯番号を記載した布を縫い付けた。さらに自宅には、玄関付近にセンサー付きチャイムを設置し、Aが玄関に近づくとチャイムが鳴り、気づけるようにした。
- 平成19年2月、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする状態で、場所の理解もできなくなっていた。
- 平成19年12月7日午後5時47分頃、A(当時91歳)は、一人で自宅を出て、排尿のためX駅のホーム先端のフェンス扉を開けてホーム下に下りたところ、列車と衝突し死亡した。
- 鉄道会社は、この事故により列車に遅れが生ずるなどの損害を被ったとして、Aの妻(当時85歳)と長男に対して損害賠償を求めた。
2.裁判所の判断
精神上の障害など一定の要件を満たす者は「責任無能力者」とされ、損害賠償責任を負わない。この場合、本人に代わって「監督義務者」がその責任を負うことになる(注3)。
本事案では、Aは重度のアルツハイマー型認知症に罹患する「責任無能力者」と認定され、Aの妻と長男が「監督義務者」にあたるかどうかが争われた。
第一審では妻と長男ともに「監督義務者」にあたると認定され、控訴審では妻のみがこれに認定された。これに対し最高裁は、妻について「精神障害者と同居する配偶者」であることを理由に責任無能力者の“法定”の監督義務者に当たるとすることはできないとして、これを否定した。
さらに、妻と長男が「法定の監督義務者に準ずべき者」にあたるかどうかの検討も行っている。妻はAの介護に当たっていたものの、本件事故当時85歳で左右下肢に麻ひ拘縮があり要介護1の認定を受けており、Aの介護も長男の妻の補助を受けて行っていた。妻は、Aの第三者に対する加害行為を防止するためにAを監督することが現実的に可能な状況にあったということはできず、その監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情があったとはいえないと判断した。
長男については、Aの介護に関する話合いに加わっていたものの、本件事故まで20年以上もAと同居しておらず、本件事故直前の時期においても1箇月に3回程度週末にA宅を訪ねていたにすぎない。そのため、Aの第三者に対する加害行為を防止するためにAを監督することが可能な状況にあったということはできず、その監督を引き受けていたとみるべき特段の事情があったとはいえないと判断した。
妻と長男いずれも、Aの「法定の監督義務者に準ずべき者」に当たらないとされた。
3.介護の実態と司法判断
本事案では、認知症患者を抱える妻と長男の監督義務者責任は否定された。とりわけ、「精神障害者と同居する配偶者」であることを理由に、責任無能力者の法定の監督義務者には当たらないとされたことは、認知症を抱える多くの家族に安心を与えたことと思う。
ただし、法定の監督義務者にあたらない場合であっても、「監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」が認められる場合には法定の監督義務者に準ずべき者として責任を問われるとしており、考慮事情として次の点が示された。
- (1)その者自身の生活状況や心身の状況
- (2) 精神障害者との親族関係の有無・濃淡
- (3) 同居の有無その他の日常的な接触の程度
- (4) 精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情
- (5) 精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容
- (6) これらに対応して行われている監護や介護の実態
これら諸般の事情を総合考慮して、その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断する。
本事案では、妻は高齢で人の手を借りてAの介護をしている状態であったこと、長男は月3回程度訪宅する関わりだったことなどを挙げ、いずれもAを「監督することは現実的に可能な状況になかった」と判断されている。言い換えれば、監督することが現実的に可能であれば責任を問われるのか。家族は何をどこまで気をつければよいのか、見えづらい。
さらにいえば、家族ではなく、医療従事者が介護をしている状況下で、今回のような事故が起きた場合はどうなるのだろうかと疑問に思う(注4)。国は在宅医療を推進しており、医療従事者が在宅を訪問する介護の形もある。また、高齢の認知症患者は複数の慢性疾患を抱えていることが多く、定期的な通院や一時入院、生活環境によっては介護施設を利用することもある。今回のケースをみても、Aはおおむね月1回程度は病院に通院し、週6回の頻度で福祉施設に通っていた。国は、高齢者は地域で支えていく仕組みづくり「地域包括ケア」政策を展開しているため、介護は家族が引受けるとは限らず、様々な人が携わる形に多様化していくことだろう。
2025年には65歳以上の5人に1人に相当する約700万人が認知症に罹患する時代がくる。多様化する介護環境において、認知症患者が自由を奪われることなく、介護者が“見守り”に携わることを萎縮することのないよう、今後も理解ある司法判断がなされることを願ってやまない。
(注1)厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要」
(注2)警視庁の調べによると、2018年度に認知症が原因で警察に行方不明届が提出された人は、1万6927人であった(令和元年6月20日)。
(注3)民法第714条1項
(注4)本件最高裁判例における木内道洋裁判官の補足意見では、「精神科病院に入院している精神障害による責任無能力者については、精神科病院の管理者が、自傷他害のおそれによる入院を引き受け、入院患者の行動制限を行う権限を有しており(精神保健福祉法36条1項)、行動制限の手続を含む処遇基準は大臣が定めるものとされている(同法37条1項)。介護施設についても、法令によって身体的拘束等の原則禁止とそれを行うについての適正手続が定められている。このように精神障害者が施設による監護を受けている場合、施設との間では、法令による定めによって、監護に関する権限とその行使基準が定められているのであり、これらの定めによる施設の負うべき義務は民法714条1項の法定監督義務に該当すると解する余地がある」とされている。