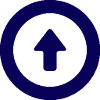人事労務 F/U NO.4
人事労務基礎講座 フォローアップ
≪判例・事例紹介、法改正情報など≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。
[事例研究]新規の治療法と医療機関に要求される医療水準
(執筆者)日本医師会総合政策研究機構 主任研究員 王子野麻代 / 日本医師会常任理事 石川広己
(法律監修)銀座中央総合法律事務所 弁護士 高山烈
医学の進歩は、救命率を高める一方、新たなリスクを生じさせる側面をもつ。たとえば、昭和40年頃から保育器が普及した。これにより従来救えなかった未熟児の命が救われるようになった。一方、保育器の酸素投与により失明等に至る未熟児網膜症患者が多数発生し、社会問題となった。保護者らは、早期に光凝固法を受けていれば失明することはなかったとして、各地で病院を訴える裁判が相次いで提起された。
当時、光凝固法は開発途上の治療法であり、その有効性や適応症例につき諸説が存在していた(注1)。これに対し、旧厚生省が統一的な指針を示したのは、昭和50年3月の厚生省「未熟児網膜症の診断および治療基準に関する研究報告」であり、同報告が医学雑誌に掲載されたのは同年8月である。
病院は、患者との診療契約に基づき、最善の注意を尽くして診療に当たる義務(注意義務)を負っているところ、新しい治療法についてどこまでの注意義務が求められるのか。その具体的な判断基準が明らかにされた未熟児網膜症姫路日赤事件を紹介する。
1.事案の概要
| 昭和49年 | 12月11日 | A病院にて未熟児として出生(在胎31週/体重1508g)。X病院新生児センターに転医し、保育器に収容され酸素投与。 |
| 12月27日 | 眼底検査を実施(異常なし):眼底に格別の変化がなく次回検診の必要なしと診断、単インするまで眼底検査は実施されなかった。 | |
| 昭和50年 | 2月21日 | 退院 |
| 3月28日 | 眼底検査を実施(異常なし) | |
| 4月9日 | 眼底検査を実施(異常の疑いあり) | |
| 4月16日 | X病院の紹介で、B病院眼科を受診した結果、両眼とも未熟児網膜症瘢痕期三度と診断された。 |
2.裁判所の判断
病院は、診療契約に基づき、人の生命および健康を管理する業務に従事する者として、危険防止のために、経験上必要とされる最善の注意を尽くして診療に当たる義務(注意義務)を負っている。そして、注意義務に違反があるかどうかは、診療当時の臨床医学の実践における「医療水準」に照らして判断される。
従来、「医療水準」は、旧厚生省の研究報告が医学雑誌に掲載された昭和50年8月時点を境界とする考えが有力であった(注1)。いわゆる「50年線引論」である。
本事案においても、第一審と控訴審はこの考え方を踏襲し、当該患者が診療を受けていた昭和49年当時はまだ光凝固法は有効な治療法として確立されていなかったのであるから、病院に注意義務違反があったとはいえないと判断した。
これに対し、最高裁は、50年線引論のみで判断した原審を否定した。そして、医療現場の通例として、新規の治療法が普及するには一定時間を要するところ、それは施設特性、地域特性、専門分野等によって差があることに言及したうえで、「医療水準」はすべての医療機関を一律に解するのではなく、「当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮」して個別に決める必要性を示した(注2)。
今回の場合、X病院の性格は、地域における新生児・未熟児医療の中心的役割を果たす存在であった。昭和33年頃に養育医療機関の指定を受け、昭和41年には新生児センターを発足させた。当該患者の診療当時(昭和49年)、光凝固装置は有していなかったが、未熟児に対して小児科と眼科が連携して眼底検査を行い、その結果未熟児網膜症が疑われる場合には光凝固法の実施が可能なB病院に転医させて判断を仰ぐ診療体制を構築していた。
他方、同一県下においてX病院と類似特性をもつ医療機関においても、X病院と同様に光凝固法の知見を有し、眼底検査の実施と転医体制が構築されていたが、眼底検査の頻度については「できるだけ早い時期に頻回に実施」する体制であった。
このことから、裁判所(差戻審)は、X病院(担当医)に対し、「未熟児に対する眼底検査を、事情が許す限り生後できるだけ早い時期にしかも頻回に実施し、その検査結果に基づき、時期を失せずに適切な治療を施すなり、本症の疑いがあればこども病院に転医させて失明等の危険の発生を未然に防止すべき注意義務を負っていた」とし、X病院(担当医)は、「わずか1回の眼底検査で以後の検診を不要とすべきではなく、頻回検査をすべきであるにもかかわらず」、それを行わなかったために、患者は光凝固法等の外科的手術の適期を失ったとして、X病院(担当医)には眼底検査義務、診療治療義務、転医義務に違反があったと判断した。
3.おわりに
(1)本事案を振り返って
本事案の特徴は、医療水準の具体的な内容を示した点である。最高裁は、旧厚生省の研究班報告が公表された時点をもって“一律に”判断する従来の考え方を改め、当該医療機関にとっての医療水準かどうかという視点から“個別に”検討する必要性を示した。その内容として、当該医療機関の性格と、所在地域における医療環境の特性(類似施設への普及状況)等を挙げている。医療機関によって地域における役割や機能はそれぞれであり、新規の治療法の普及過程における様々な差異を踏まえた最高裁の規範は、「地域医療」の実情を踏まえた実践に即した内容と思われる。
今回の場合、X病院が地域において未熟児医療の中心的な存在であり、光凝固法を前提とした眼底検査と転医による診療体制を構築していたことから、X病院にとっての医療水準が導き出された。当時、光凝固法は一般の臨床診療に用いられる途上(注1)の新しい治療法であったため、このような基幹病院でなければ結論は変わっていたことだろう。
(2)判決が医療現場に与えた影響
当時、未熟児網膜症訴訟が社会問題として注目されるなか、裁判所が転医義務(注3)を認めたことも影響し、未熟児を転医させる医療機関が相次ぎ、専門病院はオーバーフロー状態に陥る現象が起きた。
裁判所の判決が医療現場に与える影響は大きく、今回のように法的責任を意識して萎縮が生じ、医師のプロフェッショナルとしての裁量よりも、手続きを踏むことを重視する方向に働くことがある。本来の、“患者にとっての最善の医療”という本質が見失われてしまうことは回避しなければならない。本稿では詳述しなかったところであるが、医療機関において転医義務等の法的責任の考え方について理解促進を図ることは有益ではないだろうか。
(3)近年の傾向
本事案の最高裁判決が、医師の過失の一般的判断準則を述べたものとして著名である(注1)ことは確かだが、近年このような医療水準論を用いない判決もみられるようになった。その背景には、一つに症例の個別性の強さ(注4)が挙げられる。医療水準による過失判断は、未熟児網膜症のような定型的場面には有用だが、臨床経過等の個別性の大きい場面では適用を想定しにくいことを理由とする専門家の見解がある(注1)。また、当時と違って学会等による診療ガイドラインの整備が進んでいることが過失判断に影響していることから、診療ガイドラインと医療水準との関係を注目する専門家もいる(注5,6,7)。さらに、その延長の話題として、先進医療などの“水準外医療”に対する法的視点(注8)も興味深い。引き続き、来月以降に紹介したいと思う。
(注1)米村滋人「医療事故責任における高度の注意義務と医療水準」/甲斐克則・手嶋豊 編「医事法百選第2版」有斐閣, 98-100頁, 2014.
(注2)最高裁(平成7・6・9)「ある新規の治療法の存在を前提に検査・診断・治療等に当たることが、診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するには、(1)当該医療機関の性格、(2)所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきである。そして、新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において知見を有することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、その知見は当該医療機関にとっての医療水準であるというべきである。」
(注3)最高裁(平成7・6・9)「医師は、患者に対し、自ら医療水準に応じた診療をすることができないときは、医療水準に応じた診療をすることができる医療機関に患者を搬送し、又は、転医のための説明をすべき義務を負う。」
(注4)水谷渉・中島勧「判例から学ぶ第3回「医療水準」とはなんぞや」救急医学, 第43巻第7号, 974-976頁, 2019.
(注5)山口斉昭「要件事実論的視点から見た医療水準論」/伊藤滋夫編「医療訴訟と要件事実」日本評論社,6-24頁, 2019.
(注6)古川俊治「診療ガイドラインの法的意義」日本薬剤師会雑誌, 第56巻第8号, 61-63頁, 2004.
(注7)平沼直人・末石倫大「医療過誤訴訟における添付文書およびガイドラインの法的位置づけ」賠償科学No.47,96-100頁, 2019.
(注8)山口斉昭「水準外医療の選択」賠償科学No.46, 82-91頁, 2017.