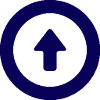人事労務 F/U NO.14
人事労務基礎講座 フォローアップ
≪判例・事例紹介、法改正情報など≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。
[事例研究]医師法21条からみる日本の刑事司法の問題点
(執筆者)日本医師会総合政策研究機構 弁護士 水谷渉
1.はじめに
医師法21条は「医師は、死体又は妊娠4ヶ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定め、その違反者に対して50万円以下の罰金が科される(同法33条の2)。
従来は、診療中の患者は届出の対象外であるとする解釈もあったが、平成6(1994)年5月の日本法医学会の「異状死ガイドライン」では、異状死体の届出対象とすべきことを明確にした。平成16(2004)年4月の都立広尾病院事件最高裁判決も、医療事故による死亡は異状死体の届出対象となることを明らかにした。
医師法21条の「異状」の解釈をめぐっては、ここ数年来、都立広尾病院事件の最高裁判決に依拠して、「外表」に異常がなければ届けなくてもよいという法解釈が医療現場に定着し、届出件数が漸減した。
しかし、この解釈に異を唱える向きもある。平成31年2月には、厚生労働省医政課長から、「死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合」には、届出せよという通知が発出された。
医師法21条は医療の畑に育っているが、その根は刑事司法という特殊な土壌に張られている。この土壌が特殊であることを注視しながら議論することこそが重要と考える。
2.死因究明制度の貧困
日本の死因究明は、刑事司法の中で司法解剖としてなされてきた側面がある。剖検率は、英米法の国々に比べるとかなり低い。監察医務院は特定の地域にしかなく、時津風部屋の暴行事件や、パロマガス機器の一酸化炭素中毒事件も、刑事捜査として死因の究明がなされてきた。
犯罪捜査目的で解剖がなされた場合、臨床医と剖検医(法医)は、被疑者と鑑定人という立場に立たされる。直接のやり取りはできず、警察を介してのやり取りとなり、死因についての詳細なディスカッションは困難となる。
本来、臨床医と解剖医は同じ医療者として協働して死因の究明を目指さなければ正しい結論にたどり着けない。しかし、刑事捜査が介入すると訴追と弁護の攻防に景色が変わり、真の死因の究明ができない。とりあえず解剖で仮決めされた死因で、訴追が始まってしまうという制度的な問題がある。
刑事捜査の土壌で死因究明がなされる限り、医師法21条の届出に及び腰になることは、やむを得ない面がある。誰しもが自分が「被疑者」になることは望まないからである。
3.黙秘権を空文化する最高裁
日本の最高裁判所は、黙秘権の保障に否定的である。麻薬取締法(現麻薬及び向精神薬取締法)では、麻薬取扱者は使用した一切の麻薬の品名、数量、交付の年月日等を麻薬業務所の帳簿に記載しなればならないとされている。麻薬を不正使用した場合にも、麻薬取扱者として免許された者が処罰されることは黙秘権侵害にならないとされている(最高裁昭和29年7月16日)。
また、道路交通法では、交通事故が発生した場合、車両の運転者に警察官・警察署への事故報告義務を課しているところ、交通事故で刑事訴追されるおそれがある場合にも、黙秘権侵害に当たらないとして、報告義務違反を処罰している(最高裁昭和37年5月2日)。
この流れからすれば、医師法21条の届出義務違反は、黙秘権侵害になりえないが、本来的にこのような処罰は黙秘権を侵害していると考えるべきであろう。最高裁が、黙秘権をきちんと機能させれば、医師法21条はそもそも違憲無効で、「異状」の解釈論自体が不要なのである。
4.自白の偏重とそれにもとづく略式起訴
医師法21条は、届出しないことを犯罪行為としているから、その立証は容易で、死体に「異状」がありさえすれば犯罪成立になる。医師法21条は、医療事故本体の業務上過失致死罪とセットで捜査されることになる。福島県立大野病院事件も業務上過失致死と医師法21条がセットで起訴されている。
これは起訴前の取り調べの時に猛威を振るう。「異状」の解釈は、捜査機関の解釈で捜査が進む。自ずと広範囲になってしまう。捜査機関の解釈では、「病死」以外は、ほとんどの外因死は「異状」たりうる。
もし、医師法21条の届出がなければ、捜査官から、「業務上過失致死で無罪だとしても、医師法21条で有罪だぞ」と指摘を受ける。一生懸命業務上過失致死罪を否定しようとしても心が折れ、業務上過失致死罪と医師法21条をセットで認めて、軽い量刑の罰金を受け入れて、穏便に終える道が選択肢に入ってくる。今後の診療所の経営、家族のこと、生活のことを考えると、不本意ながら、業務上過失致死罪を含めて、略式罰金に応じるほうがメリットが大きい状況がそこに存在する。自白をよしとする日本の刑事司法の伝統、つまり、自白したものの処分は寛容で、否認したものの処罰はとても厳しい現状が存在する。この構造は、痴漢冤罪で、自白を認めさせる捜査機関の手法と同じであり、実にアンフェアである。
届出をすれば、自分が被疑者になることが目に見えている。届けても地獄、届けなくても地獄の進退両難である。そのため、医師法21条が表面的に変わったとしても、警察への届出は、及び腰になってしまう。届出のインセンティブを欠く制度自体に再考が必要だ。
5.刑事裁判関連法規の法改正
起訴前の捜査手続きには制度的な欠陥がある。捜査の密行性という大義のもと、司法解剖がなされた場合でも、その解剖の記録は起訴されるまでは一切開示されない。起訴前の段階で、無実を立証しようにも、剖検レポートの内容がわからならければ反論ができない。仮に、剖検に間違いがあってもそれが是正されないままに起訴されることになってしまう。
また、裁判が終了しても、裁判記録のうち、検察官が提出した証拠については、目的外利用が禁止されているため、いかに不当な操作が行われてきたかを訴えるには大きな制約が存在する。司法解剖のレポートそのものは、国民の目にさらされることはないのである。
刑事裁判関係の法律を改正しようという熱意のある国会議員は少数だ。刑事訴訟法を「疑わしきは罰せず」の理論に近づけようとしても、警察・検察官僚からの反発は必至である。また、大多数の国民は犯罪と縁のない生活を送っているのであり、警察の正義を信じて疑わない。実際に現場の警察官の多くは善良だ。国会議員としても刑事法規の改正の活動は票につながらない。刑事訴訟法が、被告人に有利な改正がなされた実績は極めて少ない。
このような問題は、医療以外の業界でもいくつか生じているものと思われる。刑事司法自体が多くの問題を含んでおり、その中に医師法21条が存在している。その実態を正しく把握して、医師法21条の議論をする必要があると考える。職業上の正しい活動で訴追におびえなければならない社会は健全ではない。むしろ、正しい職業人が正当に評価される社会は、国民全体に明るい未来をもたらすと考える。